米国の地方紙に掲載された、ある技術者の訃報。その短い経歴に記された「生産管理」という言葉をきっかけに、ものづくりの根幹を支えるこの仕事の普遍的な価値と、時代と共に変化するその役割について考察します。
訃報に刻まれた「生産管理」というキャリア
米国の地方紙に、ロバート・ディラー氏という一人の人物の訃報が掲載されました。その非常に短い紹介文の中に、「production management(生産管理)」の分野でキャリアを終えたことが記されています。これは、一人の技術者がその生涯を通じて、ものづくりの現場を支える重要な役割を担ってきたことの証左と言えるでしょう。
生産管理は、ご存知の通り、QCD(品質、コスト、納期)の最適化を目指す、製造業の心臓部です。日々の生産計画の立案、資材の調達、工程の進捗管理、人員の配置など、その業務は多岐にわたります。表舞台で目立つことは少ないかもしれませんが、この機能が滞りなく機能してこそ、工場は安定的に価値を生み出し続けることができます。企業の競争力を根底から支える、まさに「縁の下の力持ち」なのです。
時代と共に進化する生産管理の手法
ディラー氏が現役で活躍されていたであろう時代、生産管理は現場の経験と勘、そして手作業の帳票や初期のコンピュータシステム(MRPなど)に支えられていました。現場の状況を肌で感じ、機械の癖や人の能力を熟知した担当者の調整能力が、計画の成否を分けた時代でした。
氏が引退された2005年頃は、ERPシステムが広く普及し、生産計画が販売や会計といった企業の基幹業務とデータで連携し始めた時期と重なります。情報の分断が解消され、より全体最適を目指す動きが加速しました。
そして現代、生産管理は再び大きな変革期を迎えています。IoTセンサーが現場のあらゆるデータをリアルタイムに収集し、AIが膨大なデータから最適な生産スケジュールを瞬時に導き出す。いわゆるスマートファクトリー化の流れは、生産管理のあり方を、事後対応型から予兆管理・未来予測型へと根本的に変えようとしています。日本の製造現場では、長年「かんばん方式」に代表されるような、現場の知恵が凝縮された洗練された手法が強みとされてきました。こうした思想や強みを大切にしながら、いかにしてデジタル技術と融合させていくかが、今まさに問われています。
技術者の引退が問いかける「知の継承」
記事には、ディラー氏が2005年に引退したとあります。これは、多くの熟練技術者が一斉に定年を迎え、その知見やノウハウの継承が大きな経営課題となった、日本のいわゆる「2007年問題」を思い起こさせます。
長年の経験を通じて培われた、個々の技術者が持つ「暗黙知」は、企業の競争力の源泉そのものです。しかし、それは意識的に「形式知」へと転換し、組織の資産として共有・継承する努力をしなければ、個人の引退と共に失われてしまう、儚いものでもあります。
現代のデジタルツールは、単なる効率化の道具にとどまりません。熟練者がどのような状況で、何を根拠に判断を下したのかをデータとして記録・分析し、その思考プロセスを次世代の技術者やAIシステムに継承するための強力な手段ともなり得るのです。一人の技術者のキャリアの終わりは、組織にとって「知の継承」という重要なテーマを改めて突きつけます。
日本の製造業への示唆
この短い記事から、私たちは日本の製造業が今まさに直面している課題と、進むべき方向性についての示唆を読み取ることができます。
1. 熟練者の経験の再評価と形式知化
現場に長年携わってきた技術者の経験や知見は、企業の代替不可能な資産です。彼らがどのような情報をもとに、いかなる判断を下してきたのかを丁寧にヒアリングし、データとして蓄積・分析することが、技術継承の確実な第一歩となります。
2. 生産管理のデジタルシフトの加速
経験と勘に頼る部分が大きかった従来の生産管理から、データを活用した客観的で予測的な管理体制への移行は、もはや避けては通れません。IoTによるリアルタイムな進捗把握、AIによる生産計画の最適化など、自社の実情と目的に合ったデジタル技術の導入を具体的に検討すべき時期に来ています。
3. 新時代の生産管理者像の構築
これからの生産管理者は、現場の知見に加え、データを読み解き活用する能力が不可欠です。ものづくりの本質とデジタル技術の両方を深く理解し、両者をつなぐことのできる人材の育成が、今後の企業の競争力を左右する重要な鍵となるでしょう。
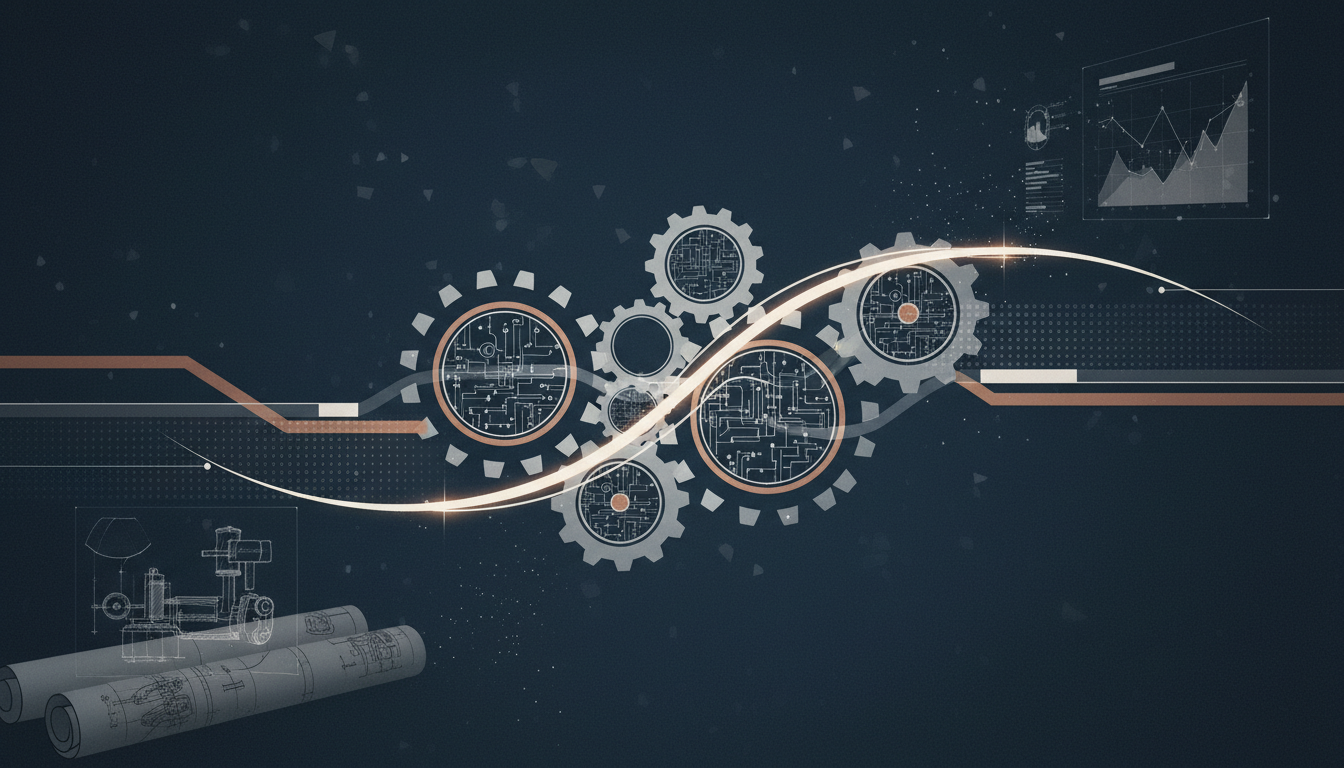


コメント