映画情報サイトIMDbに掲載された「プロダクション・マネジメント」という職務。一見、我々製造業とは縁遠い世界に見えますが、その本質は生産管理と多くの共通点を持ちます。本記事では、この異業種の事例から、日本の製造業が学ぶべき点について考察します。
映画製作における「プロダクション・マネジメント」とは
元記事で紹介されているAdari Swamy氏の職務は「プロダクション・マネジメント」です。これは映画や映像制作の現場において、プロジェクト全体を円滑に進行させるための管理業務を指します。具体的には、脚本をもとに撮影全体の予算を策定し、スケジュールを組み、スタッフやキャスト、機材、ロケーションといったあらゆるリソースを手配・管理する役割を担います。まさに、映画という製品を、定められた納期(公開日)とコスト(予算)の中で、求められる品質(作品のクオリティ)を達成するための司令塔と言えるでしょう。
この役割は、我々製造業における「生産管理」の思想と驚くほど似通っています。生産管理がQCD(品質・コスト・納期)の最適化を目指すように、プロダクション・マネジメントもまた、クリエイティブな現場を支える屋台骨として、極めて論理的かつ計画的な管理能力を求められるのです。
製造業の生産管理との共通点と相違点
プロダクション・マネジメントと製造業の生産管理。両者には明確な共通点と、そこから学ぶべき相違点が存在します。
共通点は、限られたリソース(人、モノ、金、時間)をいかに効率的に配分し、計画通りに最終成果物を生み出すかという点に集約されます。部門間の調整、進捗管理、予期せぬトラブルへの対応など、日々の業務内容は多くの製造業の管理者にとって身近に感じられるものでしょう。
一方で、相違点にこそ、我々が注目すべき示唆が隠されています。映画製作は、典型的な「プロジェクト型生産」です。毎回異なる製品(作品)を、その都度編成されるチームで、一度きりのプロセスを経て作り上げます。これは、量産や連続生産を前提とする多くの製造現場とは大きく異なる点です。天候や俳優のコンディション、監督の創造的な要求といった不確実性の高い要素を常に管理下に置き、柔軟に計画を修正していく能力は、プロダクション・マネージャーの真骨頂と言えます。また、プロジェクトごとに最適な専門家が集結する流動的な組織形態も特徴的です。
プロジェクト型生産管理からの学び
今日の製造業は、多品種少量生産やマスカスタマイゼーションの進展により、プロジェクト型の要素が強まっています。新製品の立ち上げ、特注品の製造、あるいは工場のDX推進プロジェクトなど、日常の定型業務とは異なる非定常的な業務を管理する機会は増加の一途をたどっています。
こうした場面において、映画製作のプロダクション・マネジメントの手法は非常に参考になります。刻々と変化する状況を把握し、迅速な意思決定を下す力。多様な専門性を持つメンバーを一つの目標に向かってまとめ上げるコミュニケーション能力。そして、予期せぬ制約の中で代替案を見つけ出す創造的な問題解決能力。これらは、不確実性の時代を乗り切るために、日本の製造業のあらゆる階層のリーダーに求められるスキルではないでしょうか。
日本の製造業への示唆
今回の異業種の事例から、我々日本の製造業は以下の点を再認識し、実務に活かすことができると考えます。
- 管理業務の本質の再確認
業種は違えど、管理業務の本質は「QCDの最適化」と「リソースの最適配分」にあります。自社の生産管理の在り方を、より普遍的な視点から見つめ直す良い機会となります。 - 不確実性への対応力強化
映画製作のような不確実性の高いプロジェクトマネジメントの手法は、変化の激しい市場環境やサプライチェーンの混乱に対応する上で重要なヒントを与えてくれます。固定的な計画に固執するのではなく、状況に応じて柔軟に計画を見直す「アジャイル」な発想が求められます。 - 柔軟な組織と人材活用
プロジェクトごとに最適なチームを編成するという考え方は、社内の硬直化した組織の壁を越えたタスクフォースの運営や、外部の専門家との連携を考える上で参考になります。個々の専門性を最大限に活かす体制づくりが、今後の競争力を左右するでしょう。
一見無関係に見える分野の事例であっても、その構造を読み解き、自社の課題に照らし合わせることで、新たな改善の糸口が見つかることは少なくありません。経営層から現場の技術者に至るまで、広い視野を持って他業界の優れた取り組みから学ぶ姿勢が、これからの日本の製造業には不可欠と言えるでしょう。
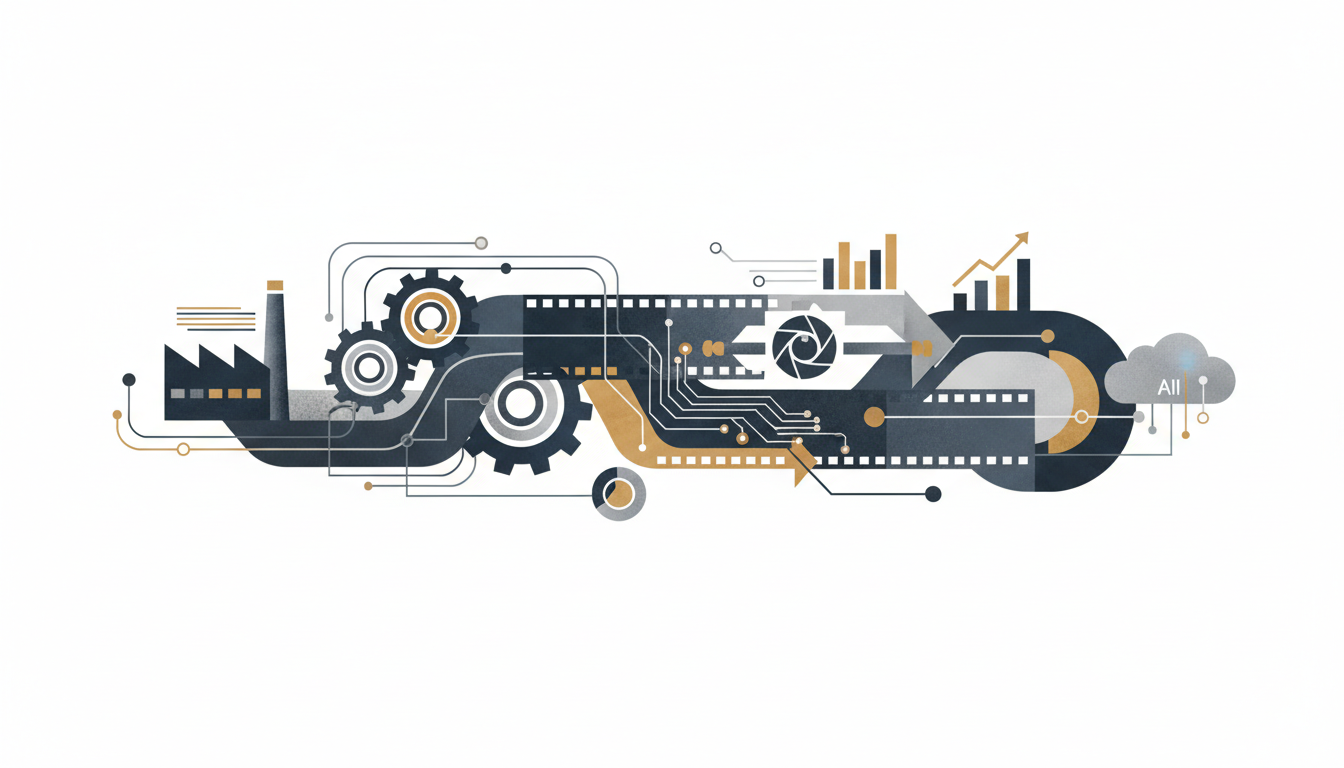


コメント