DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進において、多くの企業が「システム導入」そのものが目的化してしまうという課題に直面します。韓国の化粧品OEM企業であるCosmecca Korea社の事例は、初期の失敗を乗り越え、いかにして現場主導の改革へと転換させたか、我々日本の製造業にとっても示唆に富むものです。
DX初期のつまずき:目的の曖昧さと現場の抵抗
韓国の大手化粧品OEM/ODMメーカーであるCosmecca Korea社は、2019年から本格的なDX推進に着手しました。その第一歩として、既存の生産管理ソフトウェアの刷新プロジェクトを開始しました。しかし、この取り組みは当初、多くの日本企業でも見られる典型的な課題に直面したと言います。
まず、DXを推進する「目的」が曖昧でした。経営層には変革への強い意志があったものの、それが「なぜ必要なのか」「何を目指すのか」という具体的なビジョンとして現場にまで浸透していませんでした。その結果、DXは単なる「新しいシステムを導入すること」と捉えられ、現場からは「なぜ今までのやり方を変えなければならないのか」「新しいシステムは使いにくい」といった不満や抵抗が生まれました。経営の描く理想と、現場の日常業務との間に大きな乖離が生じてしまったのです。
転換点:「顧客価値の向上」という揺るぎない目的の設定
この状況を打開するため、同社はDXのアプローチを根本から見直しました。最大の転換点は、DXの目的を「単なるシステム刷新」から「顧客価値の向上」へと再定義したことです。そして、その目的を達成するための具体的な指標として、「リードタイムの短縮」「コストの削減」「品質の向上」という、製造業の根幹とも言える3つの目標を明確に掲げました。
このように、誰にとっても分かりやすく、事業の本質に直結する目標を据えたことで、DXは全社的な「自分たちの課題」として認識されるようになりました。「何のためにデジタルツールを使うのか」という問いに対する答えが明確になり、改革への推進力が生まれたのです。
現場主導への転換:全社を巻き込むアプローチ
目的を再定義した後、同社は推進体制も大きく変更しました。トップダウンでシステム導入を進めるのではなく、経営層から各部門の従業員までが参加するDX推進チームを結成し、現場の意見を積極的に吸い上げる仕組みを構築しました。
重要なのは、現場が自らの業務課題を発見し、その解決策を考え、必要な機能をシステムに反映させていくという、ボトムアップのサイクルを回したことです。これは、我々日本の製造業が得意としてきた現場改善(カイゼン)活動と通じるものがあります。デジタルツールはあくまで現場のカイゼン活動を支援し、加速させるための「道具」として位置づけられました。
一度に大規模な変革を目指すのではなく、現場が効果を実感できる小さな成功体験を積み重ねることで、従業員の当事者意識を高め、DXへの前向きな文化を醸成することに成功したのです。
日本の製造業への示唆
Cosmecca Korea社の事例は、DX推進における普遍的な教訓を含んでいます。我々日本の製造業がこの事例から学ぶべき要点は、以下の通り整理できるでしょう。
1. DXの目的を明確にする:「何のために」を問い続ける
DXはデジタルツールを導入することが目的ではありません。「顧客価値の向上」や「競争力の強化」といった事業の本質的な目的に立ち返り、その達成手段としてデジタルをどう活用するか、という視点が不可欠です。目的が明確であれば、現場も主体的に改善に取り組むことができます。
2. 現場を主役とした推進体制を築く
改革の成否は、実際に業務を行う現場にかかっています。経営層はビジョンを示す強いリーダーシップを発揮しつつも、現場が自ら課題を見つけ、解決策を試行錯誤できる環境を整えることが重要です。デジタルは、現場の知恵と経験を最大限に引き出すための道具であるべきです。
3. 小さな成功体験を積み重ねる
大規模なシステム導入は、現場の負担や心理的な抵抗を生みやすいものです。まずは特定のラインや工程で効果を実証し、現場が「これなら自分たちの仕事が楽になる」「品質が安定する」といった成功体験を得ることが、全社展開への強力な推進力となります。
ともすれば「手段の目的化」に陥りがちなDXですが、その本質はあくまで事業と現場の課題解決にあります。海外の事例ではありますが、この化粧品メーカーの取り組みは、我々が足元を見つめ直し、着実な一歩を踏み出すための貴重なヒントを与えてくれます。
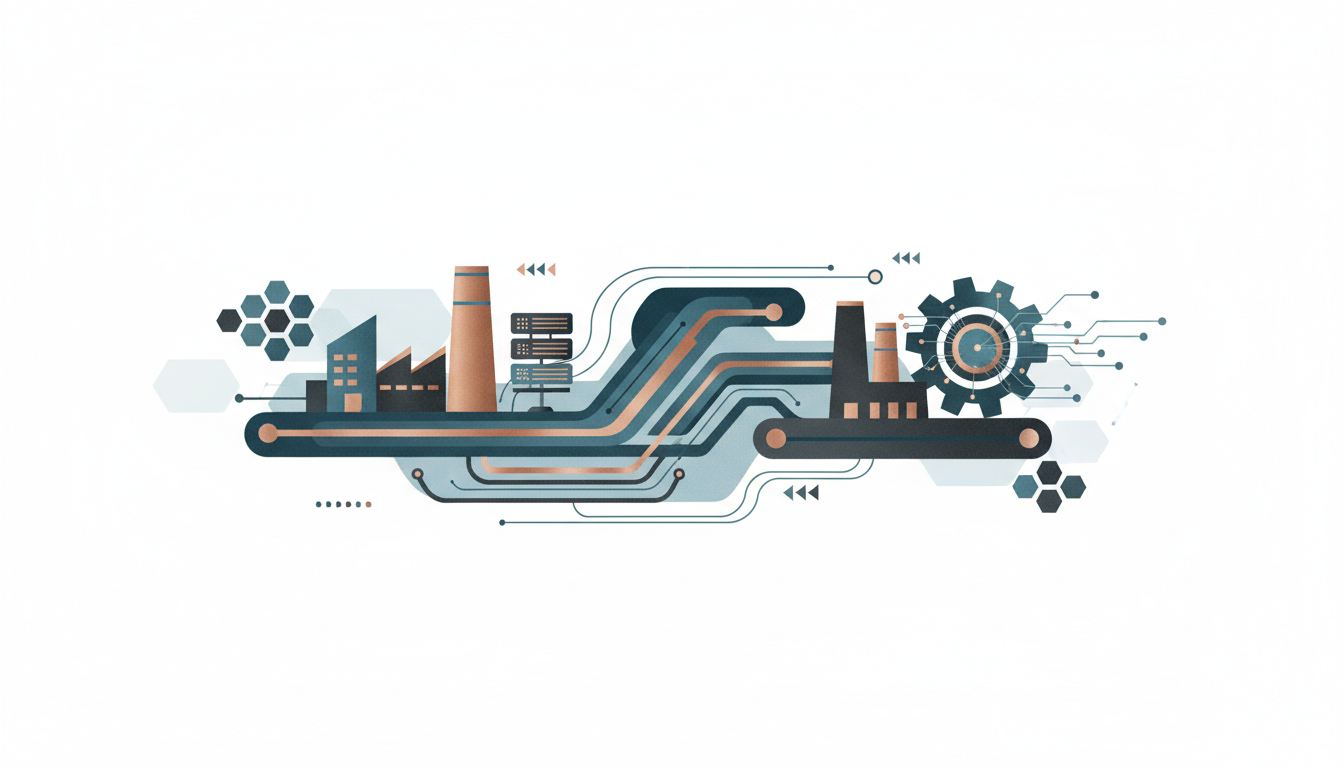


コメント